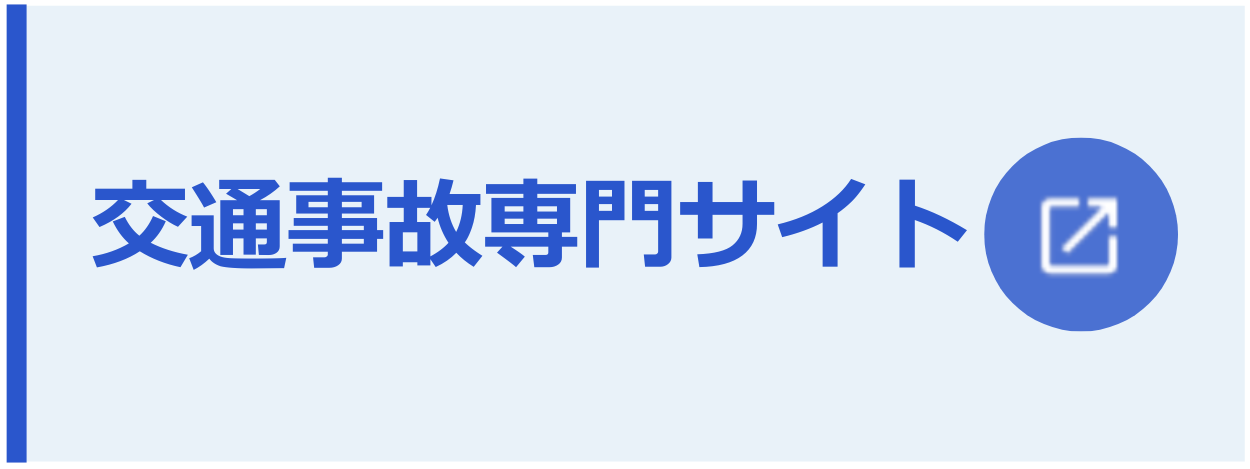歩行中に交通事故に遭った場合の注意点~交通事故に精通した弁護士が解説
目次
1 歩行者事故の特徴
⑴ 重症被害となることが多い
車同士の事故に比べて、歩行者事故では、重い怪我を負ってしまい、治療をしても後遺障害が残ってしまうことが多いです。
それは、車に乗車中の事故であれば、自車の車体が乗車中の人の身体を守ってくれますが、歩行中の事故では身体を守るものはなく、直接に加害車両に当たるため、身体への衝撃・ダメージが大きいことによります。
そのため、歩行中の事故被害の結果、お亡くなりになったり、意識不明の植物状態(遷延性意識障害)になってしまうこともあります。
頭部外傷により高次脳機能障害になってしまうこともあります。
そこまでの重症ではなくても、胸部や腹部に衝撃を受けることによって内臓を損傷することがあります。
また、手や足、背骨や腰を骨折することもあります。
もちろん、身体に大きな衝撃を受けるため、重いむちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)の症状に悩まされることも多いです。
⑵ 見落とされて轢かれるリスク、過失割合の争いリスク
歩行者は、乗用車やトラックなどの車両に比べて小さいため、とりわけ暗い夜間には加害車両に見落とされて、轢かれてしまうことがあります。
特に夜間に、歩行者が青信号に従って横断歩道を歩行している際に、歩行者の左後方から右折してきた車が、横断歩道歩行中の歩行者に気付かずに、歩行者を轢いてしまうという事故態様が目立ちます。
加害車両の運転者の注意散漫と暗い状況が相俟って原因となっていると思われますが、ただ横断歩道を渡っていた歩行者にとっては、たまったものではありません。
また、歩行者事故では、歩行者が横断歩道のない道路を横断していたり、横断歩道のない交差点内を歩行しているときに事故が起こることがあり、そのような場合には、過失割合が争いになるケースが多いことも特徴の一つです。
⑶ 損害賠償の基準
損害賠償の基準は、歩行中の事故の場合も車同士の事故の場合と変わりません。
適切な損害賠償を確保するためには、事故直後の段階からの対応が非常に重要となります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談を年間200件程度はお受けしておりますが、歩行者事故のご相談も多くお受けしております。
事故直後から必要な治療や検査、確保しておくべき証拠など、有益なアドバイスをさせていただきます。
2 歩行者事故治療の注意点
歩行者事故では、骨折など重篤なお怪我をされることが多いです。
ただ、骨折はレントゲンやCTで比較的簡単に発見できるので、治療が遅れるということはあまりありません。
見逃されがちなのが、頭部の外傷です。
重量があり速度も出ている車両に衝突された場合、頭部外傷を負うことも十分にあります。
事故直後の頭部CT検査で明らかな異常がないことが確認された結果、それ以上の精密検査がされないことがあります。
しかし、頭部CTでざっと見て明らかな所見がなくても、CT画像を精査したり、MRIを撮ったりすると、異常が発見されて高次脳機能障害だと診断される場合があります。
ところが、事故直後に医師から「異常なし」と判断されたなら、それを信じてしまうことが普通です。
しかし、事故後数日から1週間経っても以下のような症状がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。
・新しいことを覚えられない、どこに物を置いたかを忘れる(記憶障害)
・一つの事に集中できない(注意障害)
・指示されないと行動できない(遂行機能障害)
・状況に応じた行動や感情をコントロールできない(社会機能障害)
・以前に比べて怒りっぽくなった
・何かを発語しようとしても、その言葉が思い出せず、発語できなくなった(リンゴを見て、それは「リンゴ」だと分かるものの、「リンゴ」という単語が思い出せない。「失語症」といいます。)
このような場合は、再度詳細な画像検査をするとともに、高次脳機能障害に対応した医療機関で治療をする必要があります。
3 歩行者事故に強い弁護士とは?
世に起こる交通事故の多くは、車同士の事故であり、車同士の事故の場合、お怪我は打撲・捻挫であることが大多数です。
そのため、交通事故が得意であると表記している弁護士事務所であっても、骨折や頭部外傷(遷延性意識障害・高次脳機能障害)といった怪我・傷病に精通しているとは限りません。
歩行者事故に強い弁護士とは、事故直後から画像検査や各種検査を踏まえて、後々に問題となるであろう後遺障害等級の適切な認定を受けるために必要な治療や検査内容・診断書の作成を被害者やご家族に伝えることができる弁護士のことです。
また、後遺障害認定のみならず、示談交渉(損害賠償額についての相手保険会社との交渉)においても、裁判基準・弁護士基準での適切な額を主張・立証し、勝ち取れる弁護士が歩行者事故に強い弁護士といえるでしょう。
さらに、歩行者事故は、過失割合が争いになることもあります。
残された各種資料や警察の捜査資料等も精査の上、適切に過失割合を争うことができる弁護士が歩行者事故に強い弁護士といえるでしょう。
4 当事務所(河口法律事務所)は歩行者事故に強い事務所です
当事務所では、交通事故案件を業務の中心として注力しており、歩行者事故の取り扱いも豊富です。
多くの歩行者事故について適切な等級認定や裁判基準での賠償解決を行ってきました。
当事務所では、事故直後の段階から将来の後遺障害の適切な認定に向けて、必要な治療や検査、資料収集についてアドバイスすることができます。
また、大変お気の毒にも、歩行者事故でお亡くなりになられた方のご遺族からの依頼も多数承っております。
過失割合についても、防犯カメラの映像や警察の捜査資料等の開示を受ける等して、保険会社と交渉しております。
当事務所が解決した歩行者事故の解決事例
・歩行中の死亡事故で保険会社提示が約3000万円だったのを裁判で約5500万円獲得した例
・駐車場で自動車に轢かれ、足関節の機能障害、保険会社提示が約430万円だったのを約1000万円で示談した例
・道路歩行横断中の事故、足関節の機能障害で自身の人身傷害保険を活用することで、相手からの賠償と合わせて約1100万円を獲得した例
・横断歩道歩行中に轢かれる事故、頚椎・腰椎捻挫で14級認定、保険会社提示額(約175万円)が2倍近く増額した例
・ランニング中の横断歩道上で左折自動車に巻き込まれ事故、右足骨折、後遺症状の痛みで14級認定、逸失利益は15年前提で約900万円の賠償金を得た例
・歩行中に車道で自動車に轢かれた事故、腰椎捻挫等で14級認定、約400万円の賠償金を得た例
・横断歩道歩行中に赤信号無視の自動車に轢かれた事故、顔面骨折、鎖骨骨折、全身打撲等で14級認定、約600万円の賠償金を得た例
・横断歩道を歩行中、正面から右折してきた自動車に轢かれた事故、鎖骨骨折、全身打撲等で14級認定、約450万円の賠償金を得た例
・横断歩道を歩行中、正面から右折してきた自動車に轢かれ死亡、保険会社の提示額から1000万円以上増額した裁判和解で解決した例
5 早期の相談・依頼で後遺障害や過失割合を有利になる可能性があります
繰り返しになりますが、歩行者事故の後遺障害等級認定においては、早期に適切な治療や検査を受けることが重要です。
特に、高次脳機能障害については、早期に適切な検査をする必要があります。
高次脳機能障害については、意識障害に関する資料も早期に作成する必要があります(治療に日数がかかり、その間に初診時の医師が転勤してしまった等の事情で困難となる場合もあるため)。
また、過失割合が問題になる場合で防犯カメラの入手が必要な場合、1か月程度とか場合によってはもっと短期間で防犯カメラのデータが上書きされてしまうことがあるので、早期に証拠を確保する必要があるのです。
6 適切な後遺障害の認定の受け方
交通事故の後遺障害認定の申請は、「後遺障害診断書」という所定の書式の診断書と画像等の医療記録を提出して行います。
そのため、この後遺障害診断書はとても重要です。
診断書に不備や不正確・不適切な点があると、そのために本来あるべき障害等級が認定されないということもあり得るのです。
一例として、上肢関節(肩・肘・手首)や下肢関節(股・膝・足首)や指の機能障害とは、関節が曲がらなくなった場合等をいいますが、例えば、左肩の機能障害の場合、怪我のなかった右肩関節の可動域に比べて、どれくらい(何パーセント)可動域の制限があるかに着目して判断します。
「2分の1以下に制限されていれば10級」、「4分の3以下に制限されていれば12級」というように、認定基準が定められているのです。
一般的に言って、医師は治すことの方に大きな関心があり、治らなくなった障害の測定や記載にはあまり気を払ってくれないことも往々にしてあります。
そのため、例えば、関節の可動域測定は医師ではなく、その他の医療スタッフ(理学療法士など)が行うことも多いのです。
結果として、「本当はそんなに曲がらないのではないか?」というような角度が記載されていることもあります。
そうすると、上記の基準(2分の1、4分の3)にわずかに達しないために後遺障害等級が認められない、という場合があり得るのです。
このような場合、後遺障害診断書を提出する前に、後遺障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、未然に防げるケースもあり得ます。
当事務所が関わった事案でも、主治医にお願いして、本来の角度に書き直していただいた結果、無事に障害等級が認定されたことも実際にありました。
障害等級が1級違うだけで、損害賠償は数百万円単位から場合によっては数千万円も変わってくることもよくあります。
このことからも、適正な行為障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、そのための準備が非常に重要であることがおわかりいただけるでしょう。
7 適切な賠償金の獲得(示談交渉と訴訟)
歩行中の事故によって負ってしまったお怪我について、事故前と元通りに治ることが最も望ましく、元通りでなくても可能な限り回復できるに越したことはありません。
しかし、残念ながら治療の甲斐なく後遺障害が残ったり、最悪の場合はお亡くなりになってしまうこともあります。
もちろん、お身体やお命はお金には代えられませんが、元に戻らないのが現実であれば、だからこそ、適切な金銭補償(賠償)を受けなければなりません。
特に、遷延性意識障害や高次脳機能障害が残り、被害者の方の介護が必要な場合、ご家族にとっても、もしも賠償額が少なければ、この先、将来の不安が拭えないでしょう。
請求可能な損害項目を漏らさず、かつ正しく計算し、いかに立証できるかということが非常に重要です。
重い後遺障害等級が認定された場合、相手保険会社が提示する賠償額と比べて、裁判(訴訟)をした方が賠償額が上がると見込まれるケースが多いものです。
しかし、事案によっては、事前の提示額よりも裁判所が判断した金額が低くなる可能性もないわけではありません(争いごとである以上、相手の言い分が認められる可能性もあるわけです。)。
また、裁判をした場合、解決までかなりの時間がかかります。
早くても半年余り、通常は1年前後かかりますし、勝っても相手が上級審に不服申立て(控訴)をした場合にはもっとかかります。
そのため、当事務所では裁判にするか、交渉で終わらせるかはご依頼者様のご判断にお任せしています。
当事務所の方からどうすべきかのアドバイスはいたしますが、最終的にはご依頼者様の判断にお任せします。
後遺障害等級、過失割合、将来介護費、逸失利益、休業損害、基礎収入、家屋改造費などの様々なファクターについて、立証の難易度を考慮の上、どの程度の額・内容なら任意示談で解決すべきか、裁判をしたほうがよいのかといったリスクとメリット・デメリットを事前に精査してお伝えします。
当事務所から無理に裁判をすることを勧めることはいたしませんのでご安心ください。
8 初回相談は無料です。
当事務所では、被害者やそのご家族(ご遺族)の方に安心してご相談いただけるように、交通事故の初回面談相談は無料としています。
交通事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
9 弁護士報酬は後払い制です(着手金無料)
当事務所では、歩行者事故でお怪我をされた被害者及びそのご家族の方の負担が少しでも軽くなるように、弁護士費用は成功報酬制となっています。
もし、加害者保険会社からまったく賠償金を獲得できなかったら、弁護士費用のご負担はありません。
なお、被害者の方の保険に弁護士特約が付いていて利用可能な場合は、当事務所の基準に基づいてその特約を使って着手金・報酬金を計算しますが、弁護士特約が使える場合であっても、事件解決まで被害者の方に弁護士費用のご負担はございませんのでご安心ください。